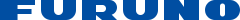- ホーム
- 車両管理ソリューション
- コラム
- DX時代だから考えたい「部分最適化でしかないソリューションベンダー」とより良いパートナーシップを築くために必要なこと
コラム・物流百景
DX時代だから考えたい「部分最適化でしかないソリューションベンダー」とより良いパートナーシップを築くために必要なこと
「さまざまなベンダーが、物流ソリューションを提案してくださるのですが...。物流プロセスにおける、ある一部分だけを改善・効率化するようなソリューションを提案されても困ってしまうんですよね」
これはある大手物流事業者がもらした愚痴です。
気持ちは分かります。導入する側としては、業務プロセス全体を一気通貫して管理できるようなソリューションの方が、いろいろと楽ですからね。
「一部分だけを改善・効率化するようなソリューション」、すなわち部分最適化を良しとするか否かについては、たびたび議論に挙がります。今回は、システムのみならず、ロボットや自動倉庫なども含めた物流ソリューション導入における部分最適化の是非を考えましょう。

バース予約システムが課題を引き起こしている??
荷待ち・荷役時間を削減するソリューションとして期待されるバース予約システム。しかし実際にバース予約システムを導入した物流センター(あるいはその物流センターを利用する運送会社)からは、「バース予約が取れない!」といった不満の声が、度々聞こえてくることがあります。
原因は、どうやら過剰な入出庫にあるようです。バース予約システムにあらかじめ設定されているバース予約可能数を、はるかに超えるバースの利用受付が発生した結果、バースの予約が取れなくなってしまっているのです。
今まで──つまりバース予約システム導入以前──は、ドライバーを待機させることでとりあえず受付だけはできていましたが、バース予約システム導入以降は、待機時間がなくなった代わりに受付すらもできなくなってしまいました。
このような課題を引き起こしている物流センターでは、庫内作業の効率化が進んでいないケースが間々あります。求められる入庫数・出庫数に対し、庫内作業の生産性が追いついていないため、バース予約システムにおける予約時間枠を増やすことができないのです。
このように、業務プロセスの中のある部分をデジタル化することで、別の問題が生じることはよくあることです。
バース予約システムを例に考えてみましょう。
- バース予約システムを導入する前
「受発注システム→WMS(Warehouse Management System)」部分がデジタル化されていた倉庫では、実際の倉庫業務における半分もデジタル化されていません。
とはいえ、一見滞りなく庫内業務は回っていました。
「デジタル化されていない」、つまり「人が行っていた」プロセスにおいて、受発注システムやWMSが発生させていたフリクションロスなどの課題を、人力で解決していたり、あるいは課題そのものが顕在化していなかったため、非効率的な部分はあれど、「一見滞りなく庫内業務は回っていた」ように見えていたのです。 - バース予約システムを導入した後
「受発注システム→WMS→バース予約システム」とデジタル化すれば、本来はバース予約システムにおける予約時間から、逆算で出庫準備を行う必要があります。
しかし、WMSでは倉庫作業員らの作業の段取りや進捗管理までは行えません。
この部分を采配する仕組み(システム的にはWES(Warehouse Execution System)の領域ですが、WESがなくとも、優秀な監督者がいれば代替できたはずです)が足りなかったことで、バース予約システムが物流センター内における一連の業務プロセスにおけるボトルネックになってしまい、「バース予約が取れない!」という不満が生じてしまったのです。
ここで挙げたバース予約システムは、部分最適化の例です。
得てして「部分最適化を積み上げると全体最適化につながる」と考えがちですが、いざ取り組んでみると、バース予約システムの事例のように、部分最適化が課題を顕在化させ、全体最適化へのボトルネックになってしまうケースも少なくありません。
「1社1ソリューション」に依存する現場がDX推進の足かせとなるケース
2025年2月、日昇会という国会議員、国土交通省・経済産業省・農林水産省・厚生労働省・デジタル庁らの職員、中小運送会社経営者が一同に介する意見交換会が開催されました。
この場で、ある国会議員が興味深い発言を行っています。
「実は一部の大手システムインテグレーターは、物流情報標準ガイドラインを快く思っていません。なぜならば、システム内のデータフィールドやプロセスが標準化されると、他社システムへの乗り換えが発生する懸念が高まるからです
むしろ、システムインテグレーターとしては自社システムをガラパゴスな状態に置き、ユーザー企業を自社に依存せざるを得ない状況を生み出して囲い込みたいと考えています」
このような日本国内における一部のシステムインテグレーターのやり方は、以前からDXの足かせとなるとして批判されてきました。
2018年9月に発表された「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」(経済産業省)では、以下のように指摘しています。
DXの足かせとなっている既存システム
DXを実行していくに当たっては、データを収集・蓄積・処理するITシステムが、環境変化、経営・事業の変化に対し、柔軟に、かつスピーディーに対応できることが必要である。そしてこれに対応して、ビジネスを変えていくことが肝要である。
しかし、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)による2017年度の調査によると、我が国の企業においては、IT システムが、いわゆる「レガシーシステム」となり、DXの足かせになっている状態が多数みられるとの結果が出ている(レガシーシステムとは、技術面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化等の問題があり、その結果として経営・事業戦略上の足かせ、高コスト構造の原因となっているシステム、と定義している)。
日本企業の多くは、根本的なビジネスモデルやシステム思想の刷新に取り組まず、部分最適化に留める小規模な改善・改修を繰り返す傾向がある。こういった部分最適化の積み上げが、DXレポートで指摘されるシステムの肥大化・複雑化やブラックボックス化につながる。
加えて、システムインテグレーターは、ユーザー企業に導入した既存システムの保守運用・改修作業によって大きな収益を上げるというビジネスモデルに固執してきました。
それゆえに既存ビジネスの枠組みを超える、ビジネスのゲームチェンジやパラダイムシフトにつながるDXソリューションを生み出そうというモチベーションが、システムインテグレーターにおいては生まれにくいというビジネス構造上の課題もあります。
先の某国会議員の発言は、まさしくこういったシステムインテグレーション・ビジネスの課題を正確かつ端的に指摘しています。
DXにおいては、システムインテグレーターとの関係性にユーザー企業側が依存することなく、主体的に課題に対して最適なソリューションを取捨選択していくことが求められます。
そして、テクノロジーの進化によって、より優れたソリューションが登場した場合には、既存ソリューションのリプレイスを図っていく勇気ある決断を行うことも必要となります。
ただしこういった取り組みでは、改善プロジェクト・DXプロジェクトの舵取りを、ソリューションベンダーやシステムインテグレーターに丸投げしてはダメです。部分最適化の積み上げを全体最適化につなげるべく、ユーザー企業側が主体的にコントロールすることが大切です。
DX時代におけるソリューションベンダーとユーザー企業の適切な関係とは
とは言え、システムインテグレーターやソリューションベンダーと、ユーザー企業では、知見の持ちようが大きく異なります。
例えば、冒頭に挙げたバース予約システムに関して言えば、ソリューションベンダーには、数多くの企業に対しバース予約システムを導入してきた経験から、「荷役・荷待ち時間の削減」のために必要な知見が豊富に蓄積されています。
対して、「これからバース予約システムを導入したい」と考えているユーザー企業には、当然ながらこういった知見の蓄積はありません。
古野電気でも、こういったジレンマに接することは少なくないそうです。
- 「車両入退管理サービス FLOWVIS(フロービス)を導入したい」
- 「新物効法における1運行2時間以内ルールに対応したいのだが、車両入退管理サービス FLOWVISは、どのようなメリット・デメリットをもたらしてくれるのか?」
例えば、この2例の問い合わせでは、古野電気がお客さまに対して貢献できる深さ・広さはまるで異なってきます。
後者(B)の問い合わせでは、古野電気の知見をフル動員した上で、場合によっては、「お客さまのケースでは、FLOWVISではなく、他社の◯◯というソリューションを導入したほうが効果が高いと思われます」というアドバイスだってできますから。
このように考えてくると、DX時代に求められるソリューションベンダー・システムインテグレーターとユーザー企業の適切な関係とは以下ではないでしょうか。
- ユーザー企業は、ソリューションベンダー・システムインテグレーターの知見を素直に、しかし正しい審美眼をもって精査すること
- ソリューションベンダー・システムインテグレーターは、ユーザー企業の痛みに正しく寄り添い、自社への利益誘導に固執しすぎることなく、ユーザー企業のDX推進に貢献すること
物流DXに正しく向き合うために必要なこと
「さまざまなベンダーが、物流ソリューションを提案してくださるのですが...。物流プロセスの中の、ある一部分だけを改善・効率化するようなソリューションを提案されても困ってしまうんですよね」
繰り返しになりますが、気持ちはとてもよくわかります。
ユーザー企業としても、ある1社のソリューションベンダー・システムインテグレーターに委ねる形でDXを実現できるのであれば、それが理想でしょう。何しろ楽ですから。
しかし、導入時にはそのソリューションが最適であったとしても、2年後、5年後も最適であるという保証はありません。
テクノロジーの進化がどんどん加速しています。特定の部分最適化ソリューションにこだわり続けることは、短期的には競争力の低下、長期的にはデジタル化・DX推進のボトルネックとなりかねません。
だからこそ、導入するソリューションが、それぞれが部分最適化であることをきちんと認識し、その全体最適化ついては自社できちんとコントロールしなければなりません。
そして必要に応じて部分最適化ソリューションの入れ替えを検討・実施するだけの度量と覚悟を、ユーザー企業は持たなければならないのです。
ただしそのためには、自社のDX推進にきちんと伴走してくれるソリューションベンダー・システムインテグレーターを選ぶことも必要となります。
一見、前述の主張と矛盾するようですが、常に切磋琢磨を怠らず、保守・改修ビジネスによってユーザー企業を囲い込もうとしないソリューションベンダー・システムインテグレーターと長期的な付き合いをすることは、DX推進と矛盾しません。
大切なのは、ユーザー企業とソリューションベンダーが依存しあう関係ではなく、お互いに切磋琢磨できる関係を築くことです。
ぜひあなたも、そういったパートナーを見つけてください。
記事のライター

坂田 良平氏 物流ジャーナリスト
Pavism代表。「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、執筆活動や、ITを活用した営業支援などを行っている。ビジネス+IT、Merkmal、LOGISTICS TODAY、東洋経済オンライン、プレジデントオンラインなどのWebメディアや、企業のオウンドメディアなどで執筆活動を行う。TV・ラジオへの出演も行っている。
※本文中で使用した登録商標は各権利者に帰属します。